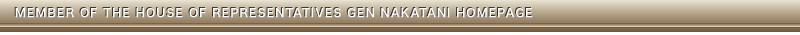活動記録
自民党静岡県連の憲法改正推進セミナーで講演。
- 2017-07-24 23:40
イタリアでは。
- 2017-07-20 07:28
フォルツァイタリア会派のブルネッタ議長、フィノッキアーロ議会関係大臣・前上院憲法問題委員長、チェルソ下院憲法委員長・下院憲法問題委員会と「五ツ星」の野党議員、ローマ大学のチェッカンティ教授と会って憲法改正について意見交換しました。
何のための憲法改正であるか、国民投票の意味をしっかりと説明し、投票選挙期間を通じて、国民からの理解・納得・共感を得なければなりません。
強く、しっかりした国防の礎を国民と共有するためにも、憲法に自衛隊をはっきりと明文化する必要があり、それを政治闘争にならぬ提案のやり方を考えていかねばなりません。
帰国前にイタリアで勤務している海上自衛隊の一等海佐の防衛駐在官と面会し、外地での勤務の激励をしました。
ジャンニーニ前教育・大学・研究大臣と懇談。
- 2017-07-18 23:25
フィノッキアーロ議会関係担当大臣と会談。
- 2017-07-18 08:23
ベルルスコーニ元大統領を党首とする、フォルツイタリアの政党代表者と面会。
- 2017-07-17 20:19
今年の下院の権限の憲法改正国民投票が否決された原因を聞いた。
憲法改正で2回の上院下院2回づつの議決が必要でその間の議論で首相の支持が低下したこと、議会のコンセンサスと多数の賛成の合意が必要であった。
ブルネッタ下院フォルツァ・イタリア会派長は、「政権が無理に改正を行ったため政権の賛否とイコールになり国民投票否決された。方法と内容は異なり、憲法改正のための国会を改めて別途開くべきだった。上院をなくすことは反対。新しい人権などユーロ導入も含めて現実と憲法には矛盾や課題が多い。
憲法によって憲法改正が規制されているが、時間と一年のマンデーとが必要である。与党と憲法改正賛成党が幅広くあること、方法と内容に関わるものがある。
できるだけ国民の意見を反映することであるが、レンティーは強引に行ったことが敗因である。
イタリア公文書館を訪問。
- 2017-07-17 17:35
スウェーデンにおいて、マリア・ストックハウス穏健党の国会議員から、憲法や国内事情について意見聴取。
- 2017-07-15 09:09
今の問題は、移民が増えてきていることであるが、シリア、エチオピア、アフガン、ソマリアから移民が入ってきているが、移民は、すぐに労働力になり、担税力もあるので、少子高齢国家として歓迎されている。医療も看護婦不足など深刻であり、それを補うものとなっている。
教育については、1歳から3歳の間に幼児教育を受けている。幼児教育は義務教育でないが、経費はかかった10%払うのみであとは政府が出している。子供の幼児教育を受ける権利はあり、両親が働いていれば受ける権利は強い。文部省で、幼児教育で何をして遊ぶかの計画が出ている。義務教育は、7才から9年間。16歳まで完全無償。スコールペンヂング。バウチャー。私立の学校に行っても無料であり、コミューン(地方)の財政から払われている。
私立も公共から許可が出ていおり、地方自治体が責任を持っている。コミューンが教育の責任を持っており、国は教育プランを作って、教育を行っている。
高校教育は、自由意志で98%の進学し、3年間教育のバウチャーがあって無償である。
大学、高等教育。ここでも授業料は、学生ローン、奨学金などを組み合わせ、誰でも学校に行けるようになっている。ローンは、働き始めてから、国に返済をしている。また、無償の手当もある。
マッツ・エイナション 元国会議員からも、憲法改正について、意見をうかがう。マッツ氏は、憲法委員会のメンバーであり、1998-2006年まで。左党。1917年。共産党。社会主義的、フェニミスト的存在であり、統治法の改革調査の専門家。憲法の問題。地方自治体の議会の政治家。ボートチルカで議会議員をしている。スウェーデンには、統治法。出版の自由に関する基本法。言論の自由。王位継承基本法の4つの基本法があり、統治法が、2008年に全廃見直しとなっている。
なぜ、統治法の全面改正がされたのかは、国民が非常に大きな不満があったわけではない。1975年以来、小さな改革をされており、全体が統一したものにするためであり、政党間の同意があったからである。
教育については、基礎的な教育は、義務教育無償。高等教育(大学)は公的機関は設置する責任・義務がある。大学教育は無償。統治法を見直す議論。グローバリズムの環境の変化で、高等教育の重要性は大きくなっている。
地方自治は明確化した。コミューンは二つあって、国よりも、地方の税の徴収は強い。戦争の緊急事態の規定があり、普段は地方の権限は侵さないが、戦争時は、コミューンの権限は停止するような規定がある。社会福祉もクオリティーが高く、高い税金で、十分な国民サービスが行われている。なぜ、国民が高い税金を払うのか。それは地方が集め、地方が使い道を決めているからである。国民は、国家よりも、地方に帰属している意識が強いのでは。
国民投票に関しては、これまで、6回の国民投票があった。EU参加はイエス。すべての国民投票は、諮問的なものであった。EUは全てが一致していたので、その通りになった。しかし、ユーロは、反対であった。
原子力発電所については、イエス・ノーでなく、選択肢を三つ持った。いろんな意見が変わってきた。その結果、どれも、マジョリティーを持つことができなかった。結果を見て国民が何を望んでいるかが不明確であった。どの違いを出すことに関して、むつかしい結果になった。その後、12あった原子力発電所は、10になって、その後新しいものは建設されていない。
国民投票については、過去、実施されているが、今後の大きなテーマでの国民投票は課題になっておらず、現時点では、国民投票をしなくとも、大きな法律の改正で変化に対応しているようである。しかし、緊急事態法や地方分権など国家としての基本的な事項は、基本的な法律に書かれており、法制度はしっかり整備されていた。
英国の憲法学の権威であるデービット・コープ教授に、英国の国民投票と解散権の制限について伺った。
- 2017-07-13 21:20
国民投票については、国民主権の中の議会主権の関係において「議員は住民、有権者のことをそのまま言うのではなく、議員に任せられたことを、国益のために考えて、発言し、行動したかどうか。」ということが大事である。
EU離脱は、英国では国民投票はすべきでなかったという声が大きい。国民投票は拘束力はないし、政府も議会も、拒否権もある。でも、それができないのは、首相が保守党の分裂を恐れて、国民投票を実施して、離脱が決まったことであり、それに反して残留にすれば、地元から反発が起きるから内閣が退陣し、離脱を決定してしまったことである。国民投票をやってしまえば、もう、覆せないのであるが、それは、国の政治として、国益を考えたことにはならない。
民主主義とは、誰が国の政策を決めるかの問題であり、住民が任せた人が国益を考えて判断すべきであり、国民投票は避けられたら、避けた方がいい。
国民は、国民投票で離脱が決まったことは、受け入れることになる。確かに、法的拘束力のある国民投票はあり得るし、国民投票は、議会が国民に返す権利であるが、それでは議会の国民からの付託に答えたものではない。それは、議員主権か国民主権かの問題であり、議員がしっかりとした将来ビジョンを考えて行動すべきである。
また、国民投票をする場合、国民への判断基準は質問の仕方も大事である。運動のしかたも重要であり、国民投票を実施する際は、公平で公正なプロセスと賛否両側をサポートすることが大切である。いかに国の意思を決めるのか、情報化やマスコミの進化した現代社会でも試行錯誤が続いている。
総じて、議会制民主主義の発祥の地英国の政治家は、政治の責任を果たすべく果敢に判断を行なってきた。国民投票の結果についても、日本と違い法的拘束力がないにもかかわらず、EU離脱という国民投票の結果に従わないという選択肢は存在しない様子だった
国民投票の結果にメディアが果たした役割とその影響について、残留を支持していた政治家には不満があるのではないかと推測していた。
ケンブリッジ大のDavid Cope 教授の見解
1.議会制民主主義の発祥の地英国の政治家は、政治の責任を果たすべく果敢に判断を行なってきた。キャメロン前首相は、保守党の事情で国民投票に答えを求めた。
2.国民投票の結果についても、日本と違い法的拘束力がないにもかかわらず、結局、反発を恐れて、EU離脱という国民投票の結果に従わないという選択肢は存在しない。国民投票の結果は結果であり、民主主義の結果を尊重する“潔さ”である。
3.日本に対するアドバイスを求めた際、国民に提示する選択肢の文言に注意するに尽きる、とのことだった。
しかし日本の場合、国民投票にかけるのは、憲法改正の文案であり、選択肢は賛成と反対と法律で決まっている。つまり、日本に工夫できるアドバイスはない、ということだと私たちは正しく受け止めなければならない。
ロンドンにおいて。
- 2017-07-13 07:00
憲法審査会海外視察。
- 2017-07-12 08:56
イギリス政治の現状は、EU残留を国会で説得できなかった保守党内の混乱にある。
元々、メイ首相は、EU残留派であったが、国民投票でキャメロン政権が、緊縮財政で弱者に厳しかった財政再建政策に取り組んでいるときに、EU残留で党内をまとめるために、EU残留の国民投票を実施したが、キャメロン政権に不満があるから、EU離脱を選んだが真相で、それで本当に良かったのか現在は、国民は、疑問を持っている。
キャメロンは、介護、医療費は高齢者に、本人負担をいれようとしたが、認知症いじめとの批判され退陣し、次のメイ首相は、人気を過信し、身内を固めるため解散総選挙を行ったが、テロ、警察予算の削減した後で、ロンドンとグラスゴーで大規模テロが発生して、無防備への反発を招いた。
労働党のジェネビ・コービンは巧みな選挙戦をし、日増しに人気がでて、保守党のメイは過半数を維持できなかった。EU離脱を主導したジョンソン外務大臣や国際貿易大臣等の離脱派への批判が大きく、労働党のコービンの方が支持率は高い。